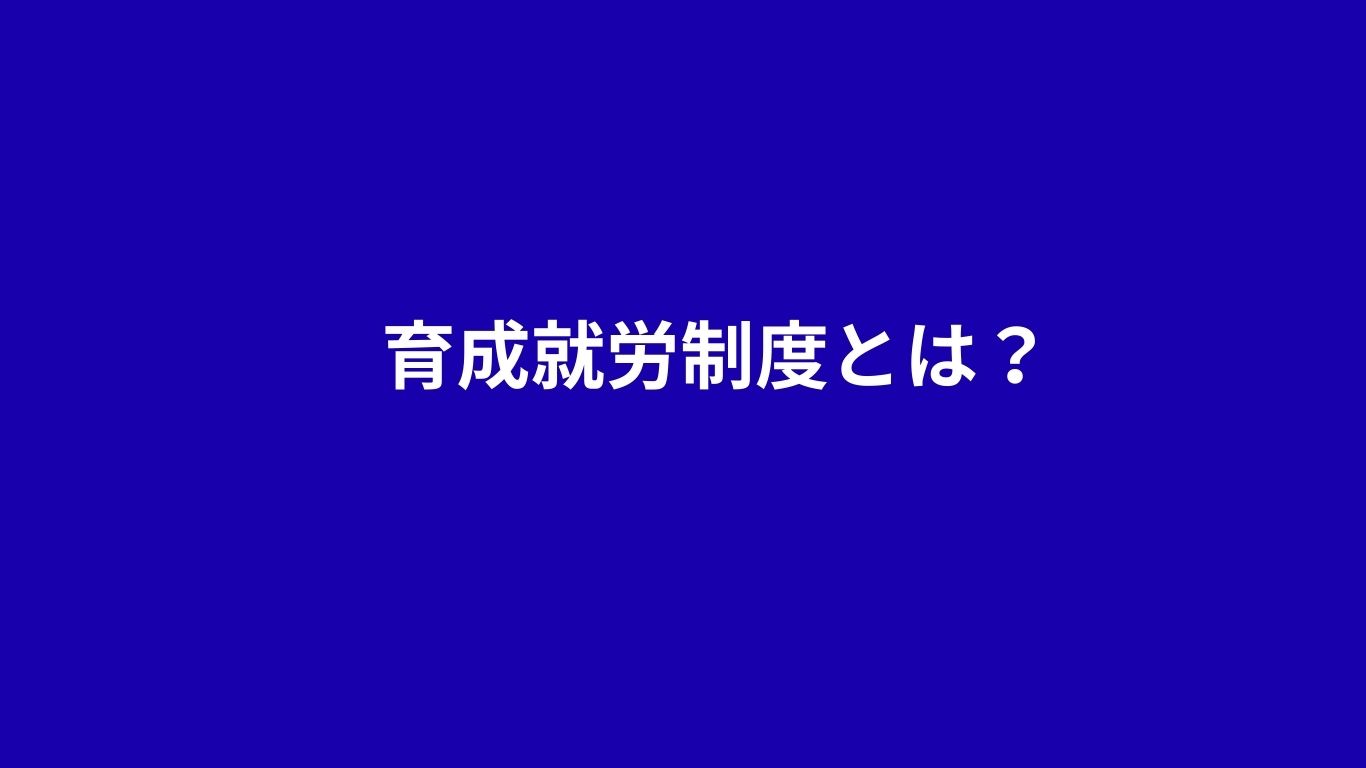解説
人手不足が続く中、外国人材の受け入れ制度が大きく変わりつつあります。育成就労制度は「職場で育て、特定技能レベルの実務力に引き上げる」ことを目的とした新しい制度で、従来の技能実習制度の代替あるいは後継として位置づけられています。本コラムでは、中小企業が知っておくべきポイント、導入のメリット・注意点、実務的な手順をわかりやすくまとめます。
育成就労制度の施行日は、2027年4月1日を予定しています。これは、2024年6月21日に関連法が公布され、公布日から起算して3年以内に施行されることが定められているためです。
施行後の約3年間は移行期間として設定されており、従来の技能実習制度から育成就労制度への移行が進められます。この期間中、技能実習生の受入れは改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3ヶ月を経過するまでに技能実習を開始するものまでとなります。
なお、育成就労制度の受入れ対象分野(育成就労産業分野)は、施行日までの間に有識者や労使団体等で構成する会議体の意見を聴いて決定されます。現在技能実習制度で認められている全ての職種・作業が育成就労制度に移行するわけではないため、自社の業種が対象となるか確認が必要です。
このように、育成就労制度は2027年4月1日の施行を目指して準備が進められており、移行期間を経て、技能実習制度は2027年6月20日までに完全に廃止される予定です。
1. 制度の要点
- 目的:日本の不足業種で人材を確保し、3年程度の就労を通じて「特定技能1号」相当の技能を身につけさせること。
- 在留資格:新たに設定される「育成就労」に基づいて就労が許可されます(分野・運用は省庁の方針に基づく)。
- 期間と移行:原則は3年の育成期間。終了後、所定の試験(日本語+技能)合格で特定技能1号へ移行可能。
- 管理体制:育成計画の認定や監理・支援体制の整備が必要で、監理支援機関や受入れ機関に求められる義務が強化されています。
2. なぜ中小企業が関心を持つべきか(メリット)
- 安定的な人手確保:欠員の穴を埋めるだけでなく、業務に即した人材を育成できる。
- 現場での教育に合致:採用後すぐに現場で教え、業務手順・品質基準を教育することで定着率向上が期待できる。
- 将来的な転換:育成終了後に特定技能に移行できれば、長期的な戦力化が見込める。
3. 事業者が負う主な責務・注意点(リスク管理)
- 育成計画の作成と認定要件:受入れ分野ごとの要件を満たした育成計画を作る必要がある。計画に基づく教育記録の保存が求められる場合がある。
- 費用負担・待遇の確保:研修・生活支援など一定のコストが発生する。賃金や労働条件は日本人労働者と同等に扱う義務がある。
- 転職・離職リスク:育成期間中や移行時に他事業所へ転職される可能性。効果的な定着施策(職場環境・キャリア設計)が重要。
- 法令遵守の重要性:不法就労助長など厳罰化の動きもあり、受け入れ手続きや報告義務を確実に守る必要がある。
4. 導入ステップ(実務チェックリスト)
- 自社の受入可否確認:育成就労の対象分野に自社の業務が該当するか確認。
- 社内体制の整備:育成担当者(指導者)を決め、教育プログラム(年間計画)を作成。
- 育成計画の作成:記載すべき項目(教育内容、評価方法、生活支援等)を文書化。
- 申請・認定手続き:必要書類を整理し、所轄の入管等へ申請(手続きは変更・追加される可能性があるため最新情報を確認)。
- 受入れ後の運用:教育記録の保管、定期評価、相談窓口の設置、労働条件の管理。
- 移行支援:3年後の特定技能試験対策(日本語と技能)と受験支援を計画。
5. 職場での“育てる”ための実務ヒント(現場向け)
- 小さな単位で仕事を分解し、チェックリスト化して反復訓練を行う。
- 日本語学習は業務に直結する表現(道具名・作業手順)を優先。外部の日本語教材より業務用ミニレッスンを用意すると効率的。
- 定期的な評価(例:3か月ごと)で到達度を見える化。達成した業務は記録に残す。
- 生活面のサポート(住居・通院・銀行口座開設手続き等)を案内し、孤立を防ぐ。
6. よくある質問
Q1. 育成就労と技能実習の違いは何ですか?
A1. 技能実習は“母国への技術移転”が主目的であるのに対し、育成就労は“日本国内で人材を育てて確保する”ことを目的としています。運用や許可の仕組み、在留のあり方が異なります。
Q2. 受け入れに特別な監理機関は必要ですか?
A2. 育成就労では育成計画の認定や監理支援体制など、従来より厳格な管理が求められます。詳細は分野別運用方針で確認が必要です。
Q3. コストはどのくらいかかりますか?
A3. 教育時間や生活支援の度合い、外部講師の有無で差が出ます。採用・教育・生活支援を含めた初期費用と月次の管理コストを試算しておくことが重要です。
Q4. 3年で本当に戦力になりますか?
A4. 仕事の性質や現場の教育体制次第です。明確に分解した教育プログラムと指導体制があれば、3年で特定技能1号相当の業務遂行力に達する見込みがあります。
7. 中小企業向けの実務的な提案(短期〜中期)
- 短期(〜6か月):現場の標準作業書(SOP)を作る/仕事分解表を用意する。
- 中期(6か月〜2年):社内指導者のトレーニングと日本語ミニ講座の整備。
- 中長期(2〜4年):人事評価に外国人材の技能到達度指標を組み入れる。特定技能移行時の試験支援プランを用意する。