【実例で解説】外国人を採用する際に企業が陥りがちな在留資格の落とし穴
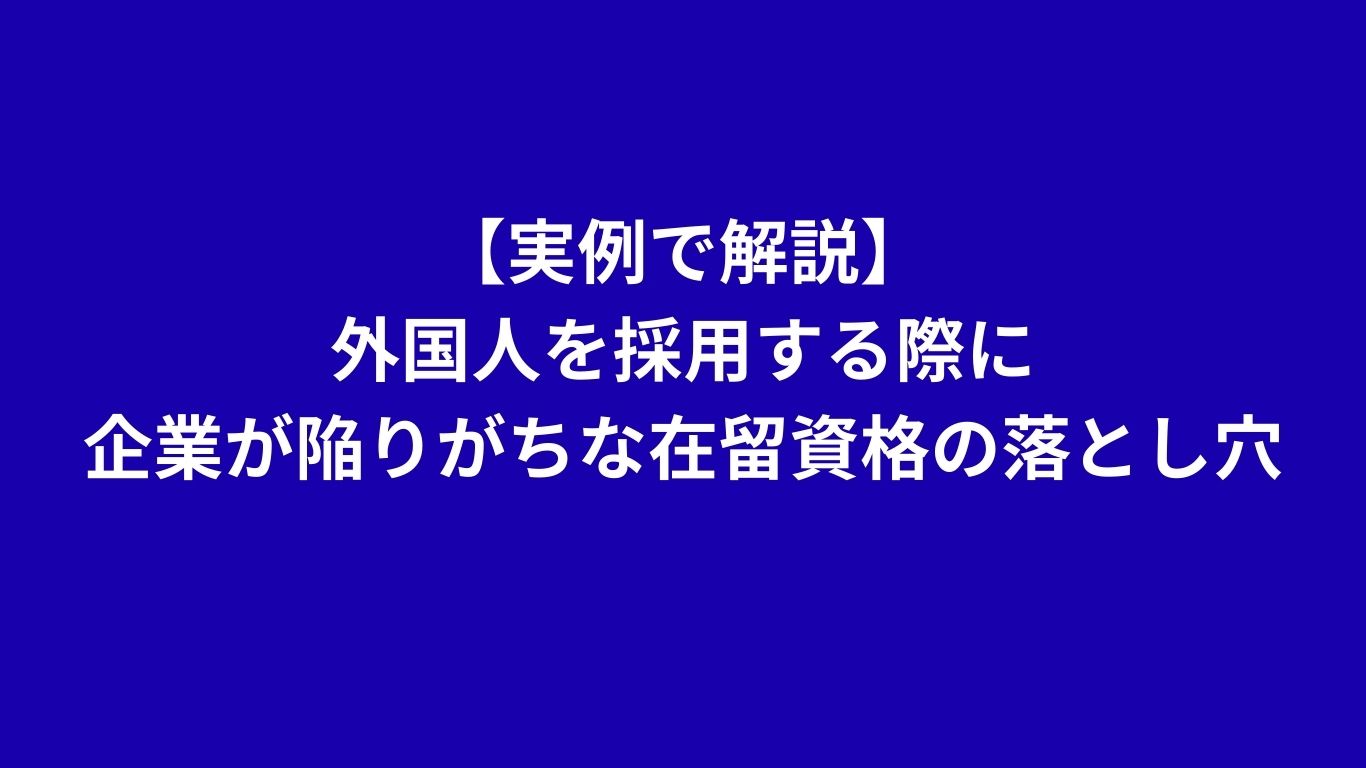
企業が外国人を採用する際に、意図せず不法就労に加担してしまうリスクや、在留資格に関するトラブルに巻き込まれるケースは少なくありません。このコラムでは、企業が実際に陥りがちな「在留資格の落とし穴」を具体的な事例を交えて解説し、その回避策を提案します。
専門家としての知見を提示することで、読者である企業の人事担当者や経営者の不安を解消し、「この事務所に相談すれば安心だ」と感じてもらうことを目指します。
目次
なぜ在留資格の落とし穴に陥るのか?
1. 落とし穴1:在留資格と実際の業務内容のミスマッチ
- よくある事例:
- 事例A(不許可事例): 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で採用した外国人社員に、入社後に単純な接客や清掃業務をさせてしまったケース。
- なぜ不許可になるのか: この在留資格は、専門的な知識や技術を要する業務に限定されるため、単純労働と判断された場合に不許可となる。
- 回避策:
- 採用前に業務内容を明確化し、どの在留資格に該当するかを正確に判断する。
- 複数の在留資格にまたがる可能性がある場合は、事前に専門家に相談する。
- 配置転換をする際も、在留資格の範囲内で可能かを必ず確認する。
2. 落とし穴2:在留期限の更新忘れと管理の甘さ
- よくある事例:
- 事例B(不法就労事例): 在留期限が切れていることに気づかず、外国人社員を働かせてしまい、不法就労助長罪に問われたケース。
- なぜ起こるのか: 外国人本人に任せきりになっていたり、社内で期限管理の仕組みが構築されていなかったりすることが原因。
- 回避策:
- 在留カードの原本をコピーするだけでなく、期限を社内の共有カレンダー等で複数人で管理する仕組みを導入する。
- 期限の数か月前から本人にリマインドし、更新手続きをサポートする体制を整える。
- 期限切れの外国人社員を雇用することは、企業の信用失墜にもつながることを強調する。
3. 落とし穴3:転職時に必要な手続きの未実施
- よくある事例:
- 事例C(不法就労事例): 他社で「高度専門職」や「特定技能」の在留資格を持っていた外国人社員を、必要な手続きをせずに採用してしまったケース。
- なぜ不法就労になるのか: これらの在留資格は、勤務先が指定されていることがあり、転職する際には改めて変更手続きが必要となる場合がある。
- 回避策:
- 採用面接時に在留カードの裏面や指定書を必ず確認し、勤務先が指定されているかどうかをチェックする。
- 転職に伴い、在留資格変更許可申請が必要になる可能性があることを事前に把握しておく。
4. 落とし穴4:留学生アルバイトの「勘違い」
- よくある事例:
- 事例D(不法就労事例): 留学生アルバイトの在留カードの期限が残っているため、卒業後も引き続き雇用してしまったケース。
- なぜ不法就労になるのか: 留学生の在留資格「留学」は、学校に在籍していることが前提。卒業や退学後はたとえカードの期限が残っていても、原則として就労はできない。
- 回避策:
- 留学生を採用する際は、必ず在籍証明書を提出させ、在籍状況を定期的に確認する。
- 卒業後の就労継続を希望する場合は、就労可能な在留資格への変更手続きをサポートする。
