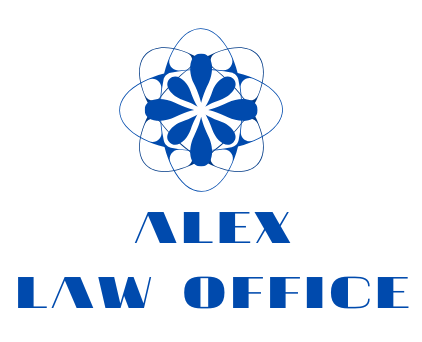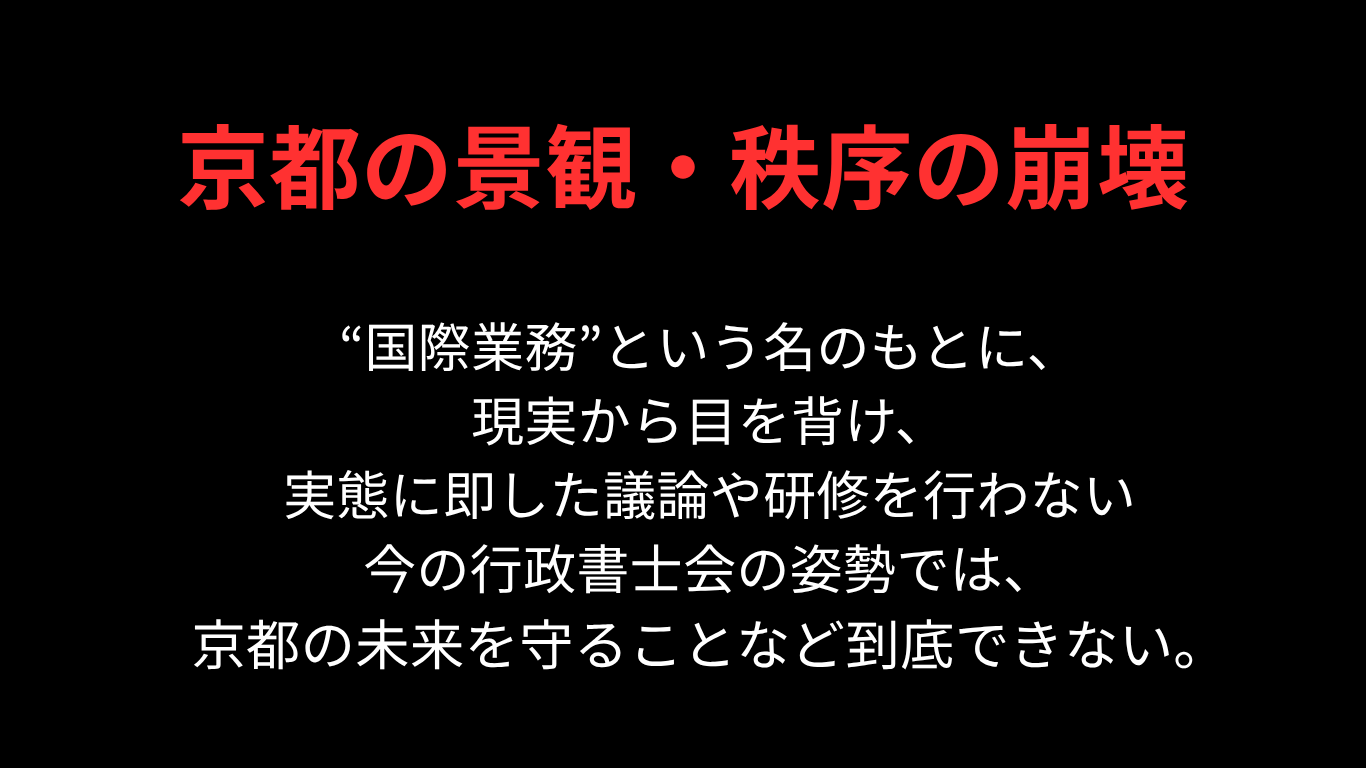本稿では、行政書士という職業が果たすべき公共性や倫理について、そして京都という都市の持続可能性との関係を見つめ直したいと思います。
近年、京都市内の一部地域では「暮らしにくくなった」と感じる市民の声が増えています。観光客の集中による混雑、住宅地の簡易宿所化、地域コミュニティの分断――これらの変化は、単なる時代の流れだけでは片付けられません。
制度の運用に携わる一人として、私はふと、こう自問せずにはいられませんでした。
この状況に、私たち行政書士が加担してはいないか?
たとえば近年、京都市内の中心部や観光エリア周辺では、中国人起業家による不動産の買い占めや、飲食・物販店舗の急増が目立つようになりました。これは、観光需要を的確に捉えたビジネス展開であり、資金力や事業遂行力の面でも目を見張るものがあります。しかし一方で、地域の生活環境への影響や文化的な摩擦も確実に生じています。
住宅が店舗へと転用され、住民が退去を余儀なくされる。生活道路が観光バスや宅配トラックで塞がれ、ゴミの分別や地域のルールが守られないまま外国語だけが飛び交う――そんな光景が、京都の“ふつうの暮らし”をじわじわと脅かしています。
そして、その“進出”の後押しをしているのが、私たち行政書士であるという事実から、目を背けるわけにはいきません。
法人設立、経営管理ビザ取得、店舗用途変更、飲食店営業許可、住宅宿泊事業――こうした法制度を熟知する私たちが、その知識を“市場拡大のツール”として提供してきた現実があります。手続きを通じて、「暮らす街」から「稼ぐ街」へと変貌させてしまった責任の一端は、明らかに我々にあるのです。
もちろん、外国人であること自体に問題があるのではありません。むしろ、文化の違いを超えて地域と共生しようとする外国人起業家も少なくありません。しかし、現実には「利益優先」で進められる事業が、地域の価値観や生活リズムを無視し、摩擦を生んでいることもまた否定できません。

専門家としての堕落
その構造の中で、行政書士が単なる「申請代行人」や「ビザ取得請負人」として振る舞っているならば、それは専門家としての堕落です。
行政書士の役割は、法令に適合させることだけではなく、制度が持つべき本来の趣旨や、地域社会との接点を見失わないよう導くことにもあります。外国人起業家支援が制度として求められる今だからこそ、単に「手続きが通るかどうか」ではなく、その事業が本当に地域に根ざし、持続可能性のある営みであるかどうかを見極める目と、伝える勇気が私たちには必要です。
私たちは“誰のための行政書士なのか”。
市民の声を無視し、制度の隙間を案内する存在になっていないか。
行政書士という職業の倫理と責任が厳しく問われる
今、京都という都市の在り方が問われていると同時に、行政書士という職業の倫理と責任もまた、厳しく問われているのです。
とりわけ京都のように歴史や景観、地域共同体に深く根ざした都市においては、「法的に問題ない」という言い訳は通用しません。行政書士が扱う“正しい手続き”が、実際には“まちを破壊する導火線”になってしまっている可能性を、私たちは直視すべきです。
このままでは、京都の各地域で人が暮らせなくなります。住民が流出し、生活の場が観光コンテンツ化し、静かに息づいてきた町並みや人間関係が崩れていく――そうした未来に、行政書士が無自覚に加担してしまうのは、あまりにも無責任ではないでしょうか。
私は行政書士として、この流れに違和感を覚える一人です。誰かがブレーキをかけなければならないとしたら、まずは制度運用の最前線にいる私たちから始めるべきではないでしょうか。
行政書士は「地域の良識」であるべき
「手続きのプロ」であると同時に、「地域の良識」であること。
それが、これからの行政書士に求められる在り方だと私は信じています。